岐阜が誇る東濃ひのきと式年遷宮
日本のヒノキは、その地域によりブランド名が付けられていることが多いですが、その中でもブランド材として知れ渡っている地域の木があります。
その中のひとつ、木曽地域で育つヒノキは全国に誇るブランド材として認知されています。
東濃ひのきとは
木曽地域のヒノキは明治時代に政府が行った森林調査で「木曽のヒノキ、青森のヒバ、秋田のスギ」が全国の森林の中でも最も優れていると評価され、現在は日本三大美林とされています。
江戸時代では木曽五木のひとつとして、伐採が制限されていました。
そもそも木曽五木はヒノキを守るため、ヒノキに似た木の伐採も禁じたため、木曽地域で一番大事とされてきたのはヒノキなのです。
詳しくはこちらの記事にもまとめておりますので、よろしければご覧ください。
江戸時代、伐採禁止になった「木曽五木」
その木曽地域は、長野・岐阜の木曽川上流のある地域を指しており、岐阜では裏木曽と呼ばれる中津川市付知・加子母・川上で産出されます。
長野県側でとれるヒノキが「木曽ヒノキ」、岐阜県側でとれるヒノキが「東濃ひのき」で、ブランド材として知られています。
元は天然のヒノキが優占する森林であり、江戸時代以降伐採が厳しく管理され、現在は国が国有林として管理しており、人の干渉を受け育成・管理され丁寧に育てられているのが東濃ひのきなのです。

伊勢神宮の御用材として
東濃ひのきの一番有名な使用用途としては、伊勢神宮です。
20年一度社を移すことで知られる式年遷宮。その建て替えのために使用されます。
式年遷宮は1300年以上の歴史を持っており、そこに用いられる材は「御杣山(みそまやま)」や「神宮備林」と呼ばれる山から供給されます。
かつては伊勢神宮が所有する「神宮林」で供給をされていましたが、伐採が進み、材が十分に確保できなかったため、何度か山を変え、ここ300年ほどは木曽川上流地域の長野の木曽谷国有林と岐阜の裏木曽国有林から伐採される「木曽ヒノキ」「東濃ひのき」を使用しています。
御用材を伐りだす年
そして今年、令和7年は第六十三回式年遷宮に使用するための御用材を伐り出し始める特別な年です。
令和15年の遷宮のため、8年前である今年から伐り出しを行うのです。
長野県では6月3日に、岐阜県では6月5日にそれぞれ伐り出すための神事が行われました。
この神事は、伝統的な伐り方「三ツ緒伐り(みつおぎり)」と呼ばれる特殊な伐採方法で、斧を使い、木を伐り出します。
三ツ緒伐りは3方向から斧を入れ、つるを3か所だけを残し、伐倒方向とは反対側のつるに最後に斧を入れることで伐倒します。
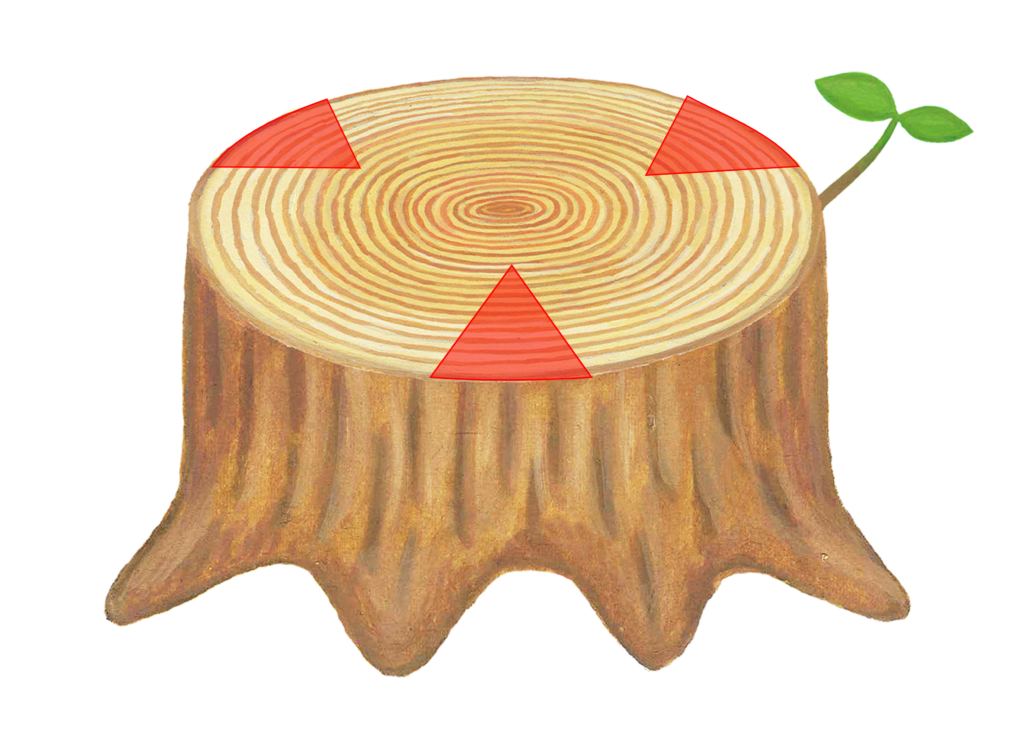
また、この伐倒方法により、神事では2本の木を伐倒しますが、その木を山に寝かせる際に「人」の文字になるよう倒れた木にもう一本の木が重なるよう伐採されます。
山は御杣山と呼ばれますが、伐る人は「杣人(そまびと)」と呼ばれ、杣人は全て白のもので身を包み、何百年も生きている木を伐り出すということで、人間が恐れ多いことをしている意を表し死んでいる者が木を倒すということから白装飾を見にまとっているとされています。
御木曳

伐り出された木は御神木と呼ばれ、御木曳(おきひき)といって伊勢神宮までの道中決められたルートを順番に回り、伊勢神宮まで運び込まれます。
基本的には神事である式年遷宮は一般人が参加することはできないですが、この御木曳は一般人でも参加できる数少ない行事です。


中津川から伐り出され御神木は6月6日から6月9日にかけて伊勢へと運びこまれました。
伐り出された次の日、6月6日は朝付知町にある護山神社を出たのち、今回は中津川駅前まで様々な場所を途中立ち寄りながら、県の重要無形民俗文化財に指定されている「木遣音頭(きりやおんど)」で練り歩きました。
ちなみに、旗や法被に掲げられている「太一」「大一」は伊勢神宮でまつられている天照大神のことを指しており、伊勢神宮に運び込む目印として掲げられています。
1300年の伝統と歴史の築かれる伊勢神宮の式年遷宮を密かに支えているのが、東濃ひのきなのです。